- 2025年10月12日
北海道で増えるヒグマ出没―自然と共に生きるために、私たちができること
北海道でヒグマの出没が増えている主な要因は、気候変動による生態系の変化と、地域社会の構造的変化(過疎化・高齢化)です。……
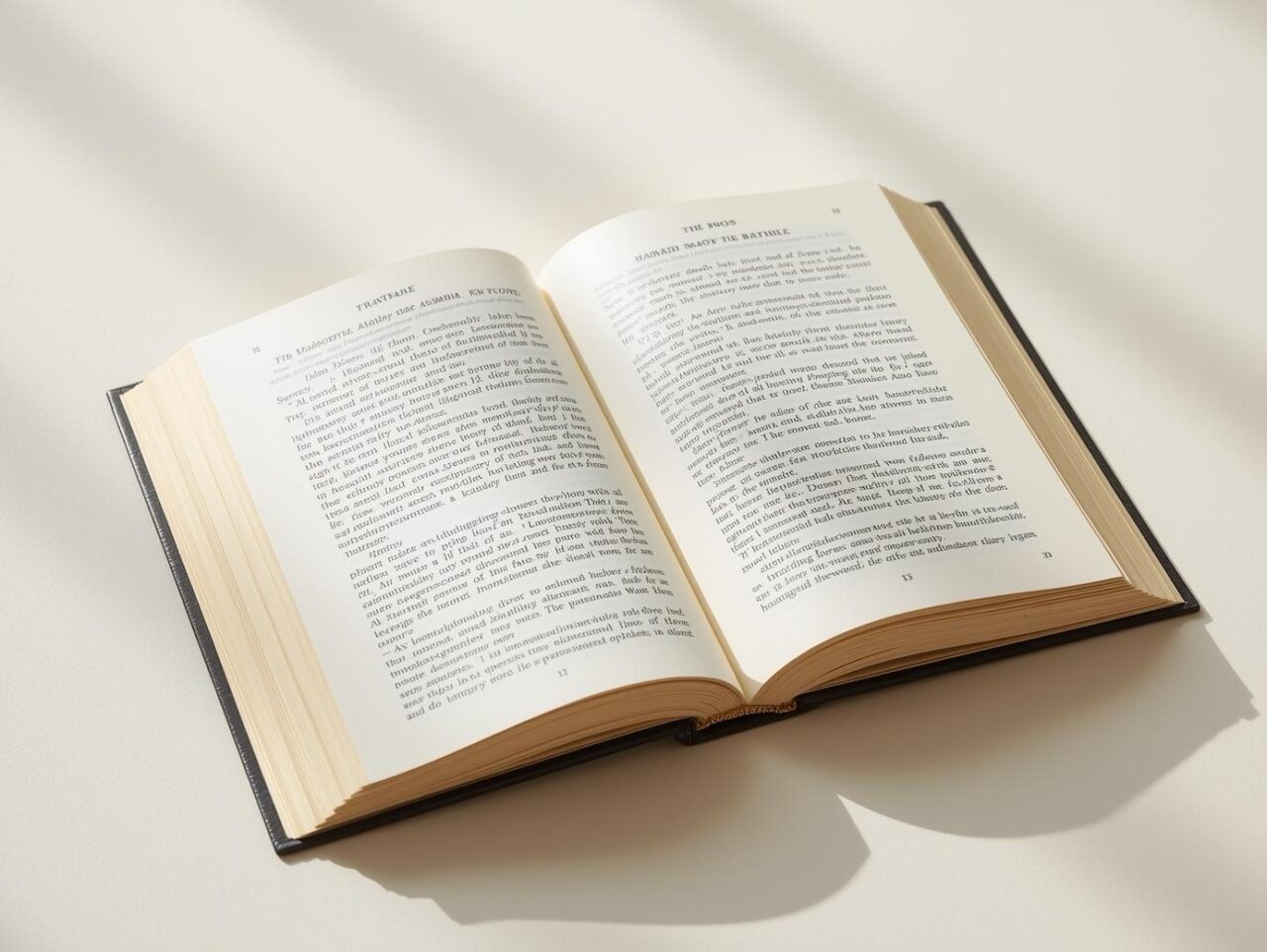

通勤途中は、マイペースに読書でインプットできる時間!
私たちの生活にインターネットが普及してから、情報収集の手段は大きく変わりました。ニュースはスマートフォンで数秒あればチェックでき、ビジネス書の要約や専門的な解説も動画やSNSで簡単に手に入ります。実際、総務省の調査によると、日本人の1日のスマホ利用時間は平均で3時間を超えており、活字に触れる時間は年々減少しています。
しかし、この「便利さ」の裏側で、文章をじっくり読み、自分の頭で考える力が弱まりつつあるのも事実です。短い情報に慣れすぎると、論理的に物事を捉えたり、深く理解する習慣が薄れてしまいます。だからこそ、今の時代にあえて活字に触れることには大きな意味があるのです。
読書をすると、文章を追いながら頭の中でイメージを組み立てる必要があります。これは「ワーキングメモリ(作業記憶)」を鍛える行為であり、思考力を高めるトレーニングになります。
例えば、ビジネスシーンで会議の議論を整理したり、複雑な問題の解決策を考えたりするとき、この力が発揮されます。また、1冊の本を読み切る過程で自然と集中力も養われます。最近では「マルチタスク疲れ」という言葉が広まっていますが、読書はその真逆。1つのことに没頭できる時間は、現代人にとって貴重なリセットの時間にもなるのです。
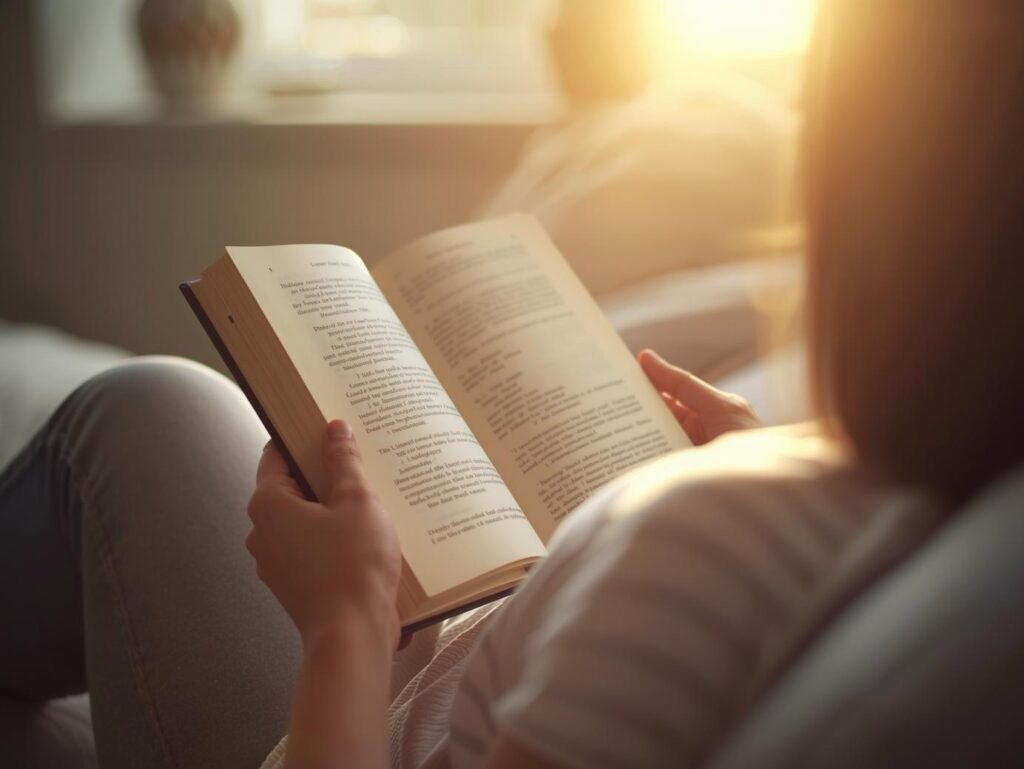
イギリスのサセックス大学の研究では、わずか6分の読書でストレスレベルが約68%も低下するという結果が出ています。音楽や散歩よりも高いリラックス効果があるとされており、心身を落ち着けるための方法としても読書は優秀です。
特に30〜40代の子育て世代は、家庭・仕事・趣味と常に時間に追われがちです。寝る前の15分を読書にあてるだけで、質の良い睡眠や翌日の集中力アップにつながることも少なくありません。
1冊の本の値段は1,500円前後が一般的です。しかし、その中に詰まっているのは、著者が何年もかけて積み上げた知識や経験です。もし専門家の講演会やセミナーに参加するとなれば、数万円かかることも珍しくありません。それをわずかな出費で手にできるのが読書の大きな魅力です。
経営者やビジネスリーダーの多くが読書を欠かさないのは、こうしたコストパフォーマンスの高さを理解しているからとも言えるでしょう。
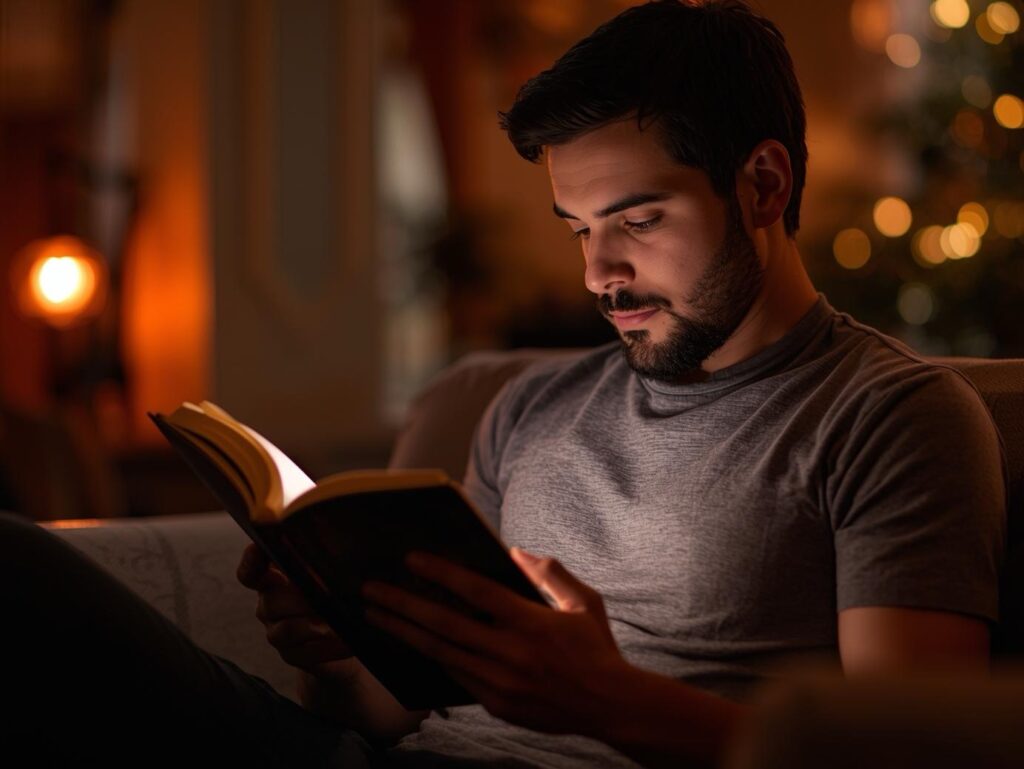
読書は単に知識を得るだけでなく、判断力を高めるためにも役立ちます。複数の著者の視点を比較したり、歴史から学んだりすることで、自分の選択肢を広げることができます。
たとえば、経営学者ピーター・ドラッカーの著書を読むことで「成果を出すとは何か」を考える視点が身につき、孫子の兵法や戦国武将の伝記からは戦略思考を学ぶことができます。こうした異なる分野の知識は、日常の仕事に新しい発想を持ち込むきっかけになるのです。
世界的に成功している人物の多くは、例外なく読書家です。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツは年間50冊以上の本を読み、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスも読書を意思決定の軸に置いていると語っています。日本でも、ソフトバンクの孫正義氏が若い頃に何千冊もの本を読破したエピソードは有名です。
読書は彼らにとって、知識を広げるだけでなく「考え方の武器」を手に入れる手段であり、それが長期的な成果につながっているのです。
読んだ内容をそのまま記憶しようとする必要はありません。むしろ、自分の仕事や生活にどう役立てられるかを意識することが大切です。
例えば、マーケティングの本を読んだら、自社の商品企画にどう応用できるかを考える。心理学の本を読んだら、部下とのコミュニケーションに活かす。こうして「読んで終わり」ではなく「読んで試す」ことで、読書は実践的な力に変わります。
子育て世代の男性は、家庭と仕事の両立で心身ともに疲れが溜まりやすいものです。そんな時に本を開けば、数分で気持ちを切り替えることができます。
読書は「能動的な休憩」と言われることがあります。テレビやSNSのように情報を受け身で消費するのではなく、自分から活字に向き合うことで、頭をリフレッシュさせることができるのです。
ビジネス書だけでなく、小説を読むことにも大きな意味があります。物語の世界に没頭することで、現実のストレスから一時的に解放され、気分転換につながります。
心理学ではこれを「カタルシス効果」と呼び、感情を浄化し心を落ち着ける効果があるとされています。仕事や家庭で張り詰めた心をゆるめる手段として、物語の読書は非常に有効です。
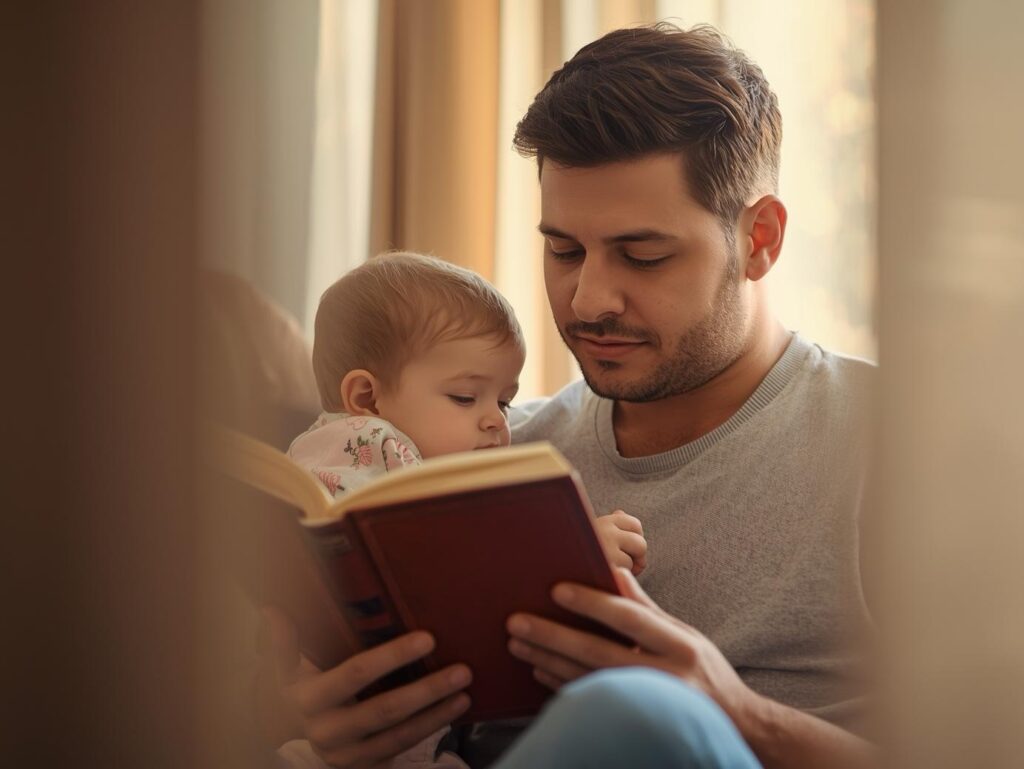
子育てをしていると、どうしても自分の価値観や経験だけで子どもに接してしまいがちです。しかし教育関連の本やエッセイを読むことで、新しい考え方や他の家庭の事例に触れることができます。
「こんな接し方もあるのか」と気づくだけで、子どもとの関わり方が柔らかくなったり、夫婦間の会話が深まることもあります。読書は、親としての成長にもつながるのです。
読書習慣をつけたいと思っても、「時間がない」と感じる方は多いでしょう。ですが、1日15分でも十分に読書は可能です。
通勤電車、昼休み、子どもが寝た後のわずかな時間。この「すき間」を読書に充てるだけで、年間にすると90時間以上の読書時間が生まれます。これは文庫本なら30冊以上に相当します。
紙の本を読むのが難しいときは、電子書籍やオーディオブックが便利です。スマホやタブレットに入れておけば、ちょっとした待ち時間にも読書ができます。
特にオーディオブックは、家事やジョギング中でも「ながら読書」ができるため、子育て世代の強い味方になります。
読書を習慣化するには「気が向いたら読む」ではなく、あらかじめ予定に組み込むことが有効です。
例えば「寝る前に15分読む」「朝のコーヒーを飲みながら10ページ読む」と決めるだけで、読書が生活リズムの一部になります。
家族と過ごす時間を大切にしながらも自分の時間を確保するには、ルーティンを工夫することが必要です。子どもと一緒に本を読む「読書タイム」を設ければ、親子で楽しめる上に習慣化にもつながります。
仕事の成果を高めたいなら、マーケティング・経営・心理学といったジャンルが定番です。例えば『イシューからはじめよ』(安宅和人)は、問題解決の視点を磨く名著として多くのビジネスパーソンに支持されています。
日々の疲れを癒すなら、エッセイや心理学関連の本が役立ちます。特に『スタンフォードのストレスを力に変える教科書』は、ストレスを悪者にせず活かす方法を学べる一冊です。
エンターテインメント性を重視するなら小説や歴史書。たとえば池井戸潤の企業小説は、ビジネスのリアルとドラマチックな展開を同時に楽しめます。歴史書なら司馬遼太郎の作品が、知識とロマンを与えてくれるでしょう。
『子どもへのまなざし』(佐々木正美)など、教育や心理に関する本は、子育て世代にとって学びが多い分野です。子どもとの向き合い方に悩んだときの指針として、一冊持っておくと安心です。
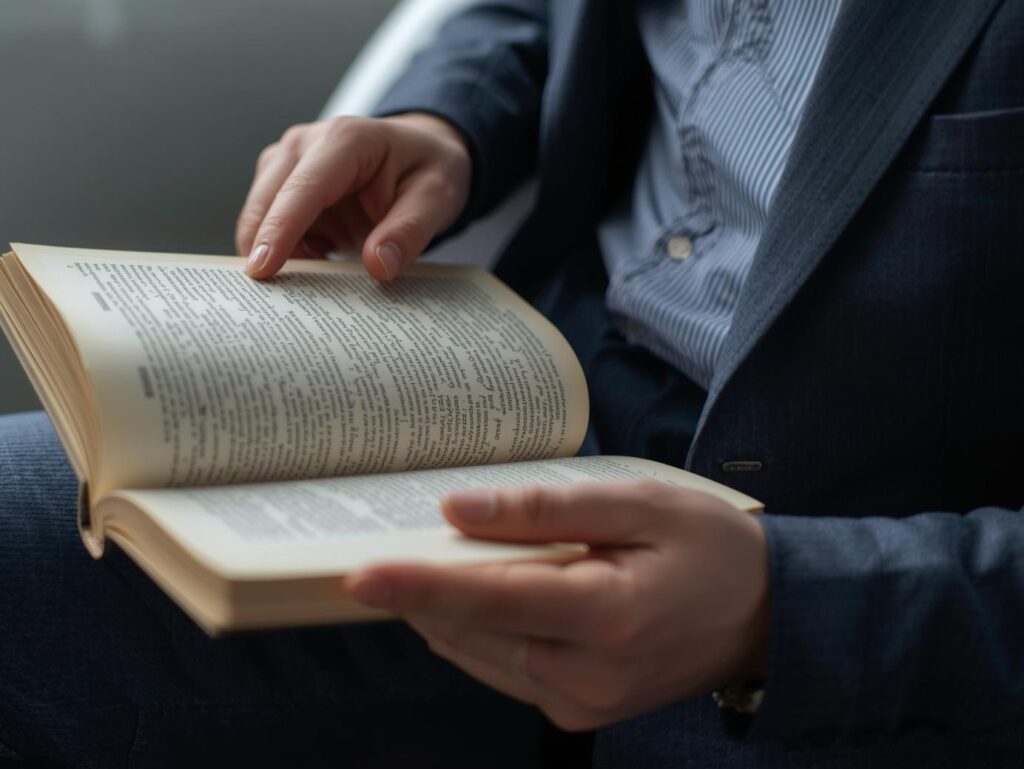
インターネットが便利になった今だからこそ、あえて本を開くことに大きな価値があります。読書はビジネスに役立つ知識を与え、ストレスを和らげ、親としての成長も助けてくれる「最高の自己投資」です。
1日15分の読書習慣が、1年後には大きな力に変わります。忙しい30〜40代だからこそ、活字に触れることで自分らしさを取り戻し、人生をより豊かに輝かせてみてはいかがでしょうか。
コメントを書く