- 2025年9月16日
物価高・円安時代にこそ考えたい―ANA・JALマイル活用で広がる30〜40代男性のライフスタイル戦略
物価高と円安で海外旅行が難しくなっている今だからこそ、マイルを活用した賢い旅行計画が注目されています。出張や日常生活でA……
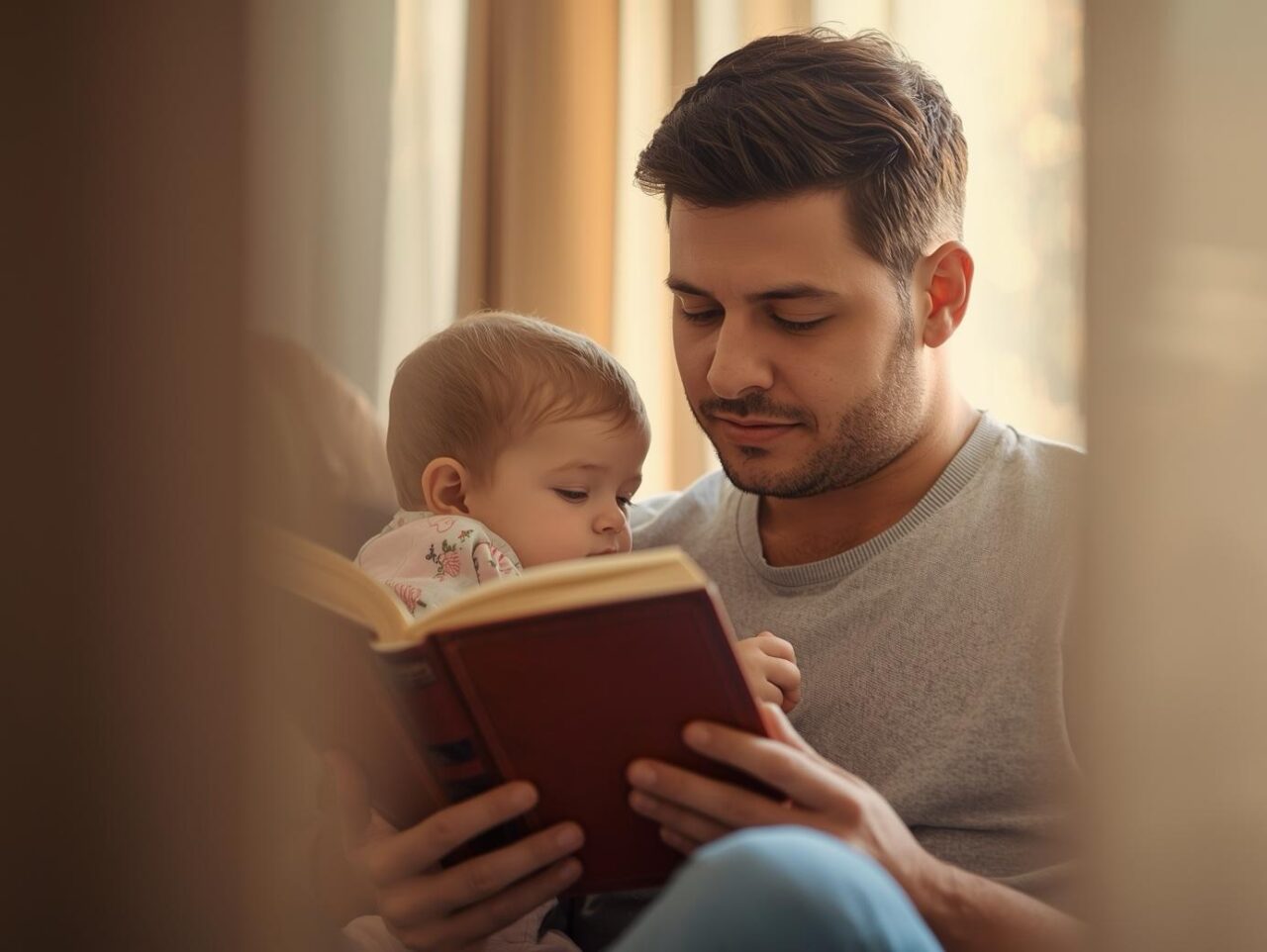

今日は何が読みたい?幼稚園でピザづくりしたから、ピザの本にしようか?
言葉を覚える時期の子どもにとって、絵本は生きた教材です。たとえば「おおきなかぶ」や「ぐりとぐら」のような繰り返し表現の多い絵本は、自然に言葉を吸収できる仕組みになっています。
文部科学省の調査では、就学前に週3回以上の読み聞かせを受けていた子どもは、小学校低学年での国語テストの平均点が約10%高いという結果も出ています。単に単語を覚えるだけでなく、会話で使える言葉の幅が広がり、自分の気持ちを正確に伝える力(表現力)につながるのです。
例えば、4歳の子どもが「うれしい」だけでなく「わくわくする」「ほっとする」と言えるようになると、感情をより細かく伝えられます。これは読み聞かせの中で「登場人物の気持ち」を繰り返し聞いてきたからこそ育つ力です。
物語を理解しながら聞くことは、子どもの読解力を高めます。たとえば「なぜお姫さまは悲しんでいるのかな?」と問いかけながら読むと、子どもは登場人物の行動や感情を筋道立てて考えるようになります。
また、絵本には文字だけでなくイラストも添えられています。文字情報と視覚情報を同時に受け取ることで、脳の処理が活発になり、イメージを頭の中で膨らませる「想像力」が育ちます。
心理学者ブルーナーの研究では、幼少期に想像力を育んだ子どもは、将来的に問題解決能力や創造性が高まる傾向があるとされています。これは「ただ読む」だけではなく、父親が声に抑揚をつけたり、間をとったりする工夫によって、子どもの想像力をさらに刺激できるのです。
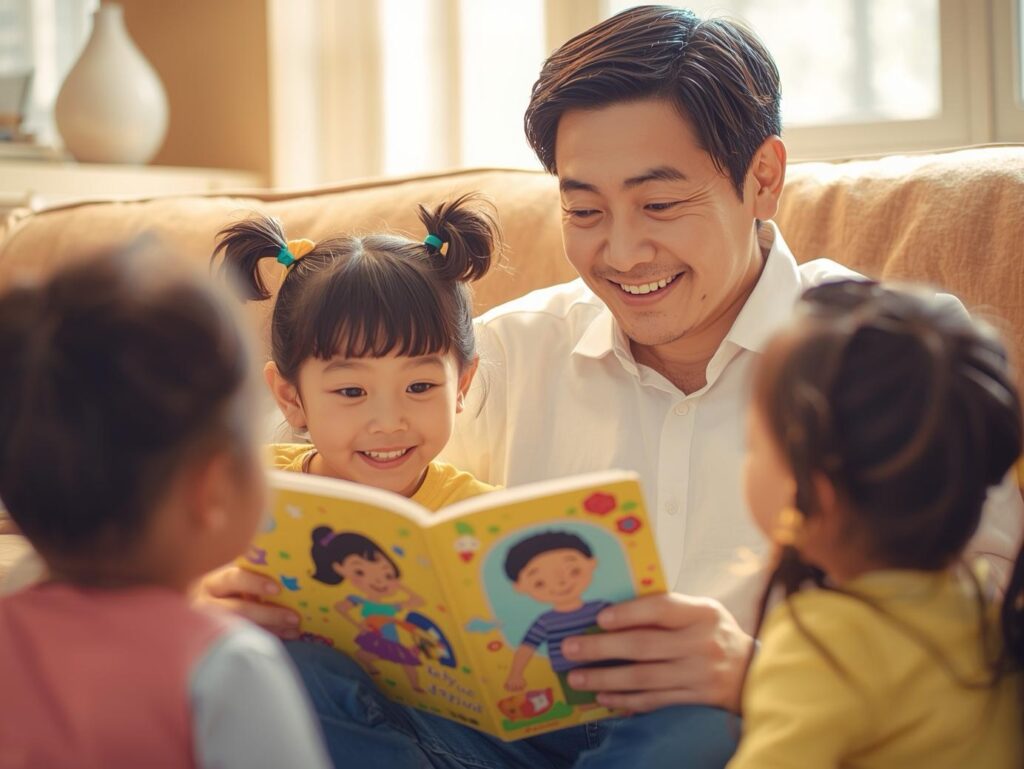
読み聞かせの最大の魅力は、親子の心をつなぐ時間になることです。
絵本を通して「登場人物の気持ちを一緒に考える」ことは、子どもに共感力を育てます。たとえば、物語の中で友達を助けるシーンを読んだとき、「もし君だったらどうする?」と問いかけると、子どもは相手の立場を想像し、思いやる心を学びます。
さらに、父親が隣で本を読んでくれる時間は「自分のためだけに用意された特別な時間」として子どもの心に刻まれます。NHK放送文化研究所の調査によると、親子で読み聞かせをしていた家庭は、思春期以降も親子関係が良好に保たれる割合が20%以上高いと報告されています。
つまり、読み聞かせはただの教育的行為ではなく、長期的な絆づくりにつながるのです。

父親にとって、平日は仕事で帰宅が遅くなることも少なくありません。しかし、寝る前の10分だけでも読み聞かせをすれば、子どもにとっては大切な「一日の終わりの安心時間」になります。
例えば、ある30代の会社員男性は「毎日帰宅が21時過ぎになるが、寝る前に一冊だけ絵本を読むことを習慣にしている。子どもが『パパが帰ってくるのを待ってる』と言ってくれるのが何よりの励みになる」と話しています。
短時間でも「父親と過ごす特別な儀式」となることで、親子の信頼関係は確実に深まります。
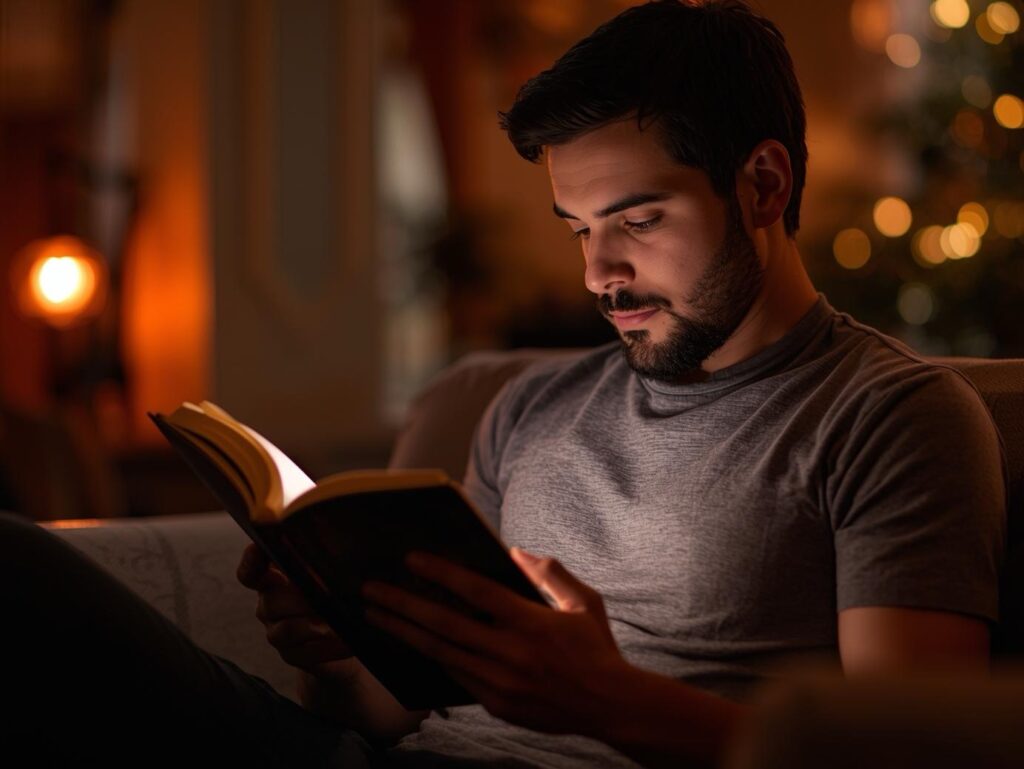
父親が選んだ絵本には、その人の価値観や趣味が反映されます。冒険物語を好む父親なら、子どもも自然と挑戦や探求を楽しむ姿勢を学びます。動物の絵本を選べば、命の大切さを考えるきっかけになります。
父親が「なぜこの本を選んだのか」を少し語ることで、子どもは父親の考え方を知り、親子の会話が深まります。これは単なる読み聞かせ以上に、「親子で価値観を共有する場」としての意義を持つのです。
子どもにとって「自分で選んだ本を読んでもらう」ことは大きなモチベーションになります。本棚を低い位置に置き、表紙が見えるように並べると、子どもは自然に興味を持ちます。
また、休日に一緒に図書館や書店へ行き、「今日はどの本にしようか」と選ぶ時間自体を楽しむのもおすすめです。選んだ本を大切にする姿勢が身につき、読書習慣の基盤にもなります。
単調に読むよりも、声色や抑揚をつけることで物語の世界に引き込むことができます。例えば「オオカミだぞ〜!」と低い声で読んだり、ドアをノックする場面で実際に「コンコン」と音を立てたりするだけで、子どもは夢中になります。
さらに「次はどうなると思う?」と問いかけながら進めると、子どもの想像力や会話力を引き出すこともできます。
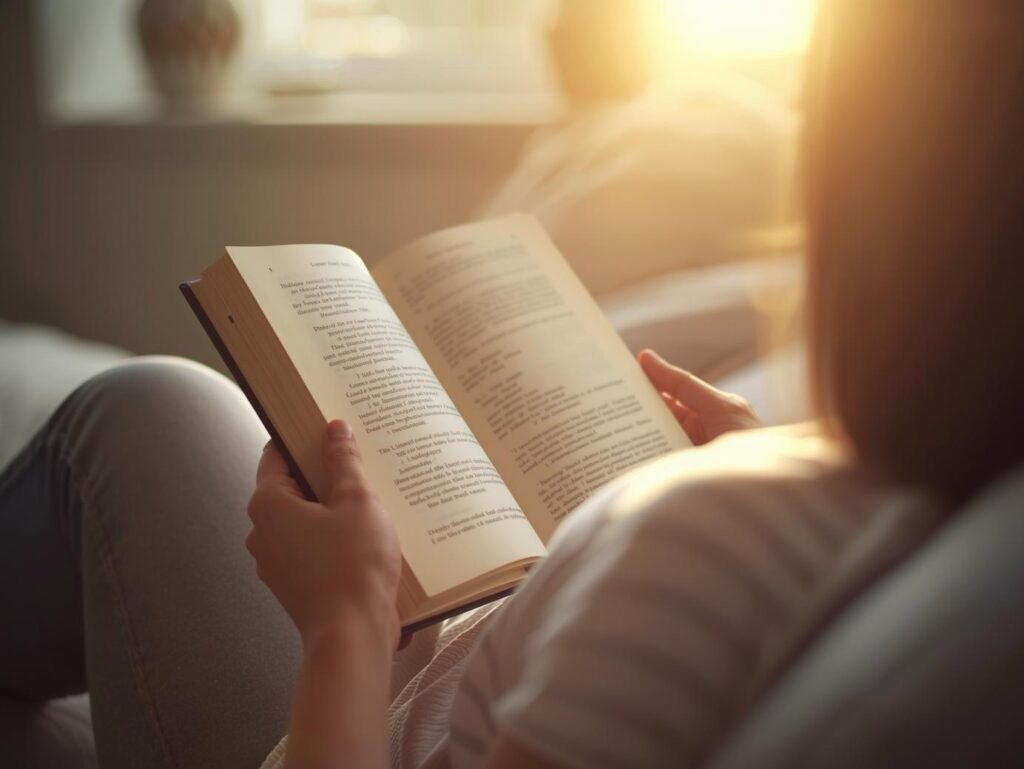
父親と母親で得意なジャンルを分けるのも効果的です。たとえば、父親は冒険や科学系の絵本を担当し、母親はリズム感のある絵本や詩を担当すると、子どもは多様な表現に触れられます。
また、週末に「家族みんなで読み聞かせの会」を開くのもおすすめです。兄弟や祖父母も加わると、本が家族のコミュニケーションの中心になり、楽しい習慣として定着します。
子どもが飽きている様子を見せたら、無理に続けず「今日はここまでにしよう」と切り上げることも大切です。読み聞かせは「楽しみ」であって、「勉強」や「義務」になってはいけません。
短い本でも、毎日少しずつ続ける方が効果的です。
親が「教育的に良いから」と選んだ本だけを押し付けてしまうと、子どもは本自体に苦手意識を持ってしまいます。もちろん名作絵本を取り入れるのは大切ですが、恐竜図鑑や電車の本など、子ども自身の興味を尊重することが何より重要です。
最近ではタブレットやスマホの読み聞かせアプリも普及しています。これらは便利ですが、親子で顔を合わせてやりとりできる「紙の本」ならではの温かさは代えがたいものです。
デジタルは補助的に活用しつつ、親子の対話を大切にすることがポイントです。
読み聞かせは子どもの語彙力・表現力・読解力・想像力を育み、共感力や絆を深める最高の習慣です。そして、それは子どもだけの成長につながるものではありません。
父親自身も、物語を読む中で表現力が磨かれ、会話が豊かになり、日常の中で「想像力を働かせる視点」を持てるようになります。
忙しい毎日だからこそ、1日10分の読み聞かせは「父親のスタイルアップ」にもなるのです。
ぜひ今日から、寝る前のひとときを「子どもと一緒に物語の世界へ旅立つ時間」に変えてみてください。
コメントを書く